トレンド&テクノロジー / デジタルコンテンツの未来〜温故知新〜
第13回:富岡 聡(カナバングラフィックス代表/CGプロデューサー/ディレクター)
- アニメ
- コラム
- 映画・TV

CGと縁の深い方々にお話をうかがい、デジタルコンテンツの未来を見通していく記事をお届けする本連載。今回は有限会社カナバングラフィックス代表の富岡聡氏に登場いただいた。『ウサビッチ』や『イナズマデリバリー』など、グラフィカルで個性豊かなキャラクターのアニメオリジナル作品をいくつも手掛ける同社は、業界で独自のポジションを築いているといえる。その理由は富岡氏の作家性と、マーケティングに裏打ちされたリーダーシップに基づくもの。キャリアを振り返りつつ現在の仕事や海外へ向けた施策、会社の未来まで語ってもらった。
【聞き手:野口光一(東映アニメーション)】
Supported by EnhancedEndorphin
子供の頃から絵本とマンガを描き、学生時代からCGの道へ
東映アニメーション/野口光一(以下、野口):カナバングラフィックスの代表作である『ウサビッチ』や『イナズマデリバリー』は、いずれもビビッドな色遣いが特徴的で、これは富岡さんが幼少期にアメリカで過ごされたことが影響しているのかなと思ったのですが、ご自身ではどのように捉えていますか?
富岡聡(以下、富岡):私がアメリカにいたのは2歳から3歳までの一年間だったので、さすがに覚えてないですね(笑)。ただ、アメリカにいる時に母親がよく絵本を読んでくれたことが関係しているかも知れません。当時スーパーマーケットに行くと絵本をたくさん買ってくれたのですが、その中の1冊に影響を受けていることに、だいぶ後になって気づきました。リチャード・スカーリーという方の『Great Big Mystery Book』という本で、豚のダットリーと猫のサムの探偵2人組が事件を解決していくというお話です。とても気に入っていて、ボロボロになった後も、本を修理してくれる工場に出してもらってまで読んでいたほどです。
富岡:2人組のキャラクターとか、丸いキャラクターが好きなのもこの絵本の影響から来てるのかなと。その後、日本に帰ってきたあとに幼稚園で絵本を描いていて、藤子不二雄先生に憧れて小学4年生ぐらいからマンガを描き始めました。そこから10年くらい漫画を描いて応募を繰り返したのですが、佳作止まりだったのでその道は諦めました。でも何らかの商業美術に関わりたくて、大学の時にデザイン事務所でアルバイトをしたんです。当時は、やっとパソコン上でグラフィックができるようになった時代で、全部買えば数百万円するMacintosh、Illustrator、Photoshopが使えるとあって、アルバイト代は微々たるものでしたが、とにかくその機材を使いたい一心で仕事をしていました。ところが、そのバイトしていたデザイン事務所が、とある事情でなくなってしまって。
野口:別のアルバイト先を探すことに?
富岡:はい。当時はアルバイト雑誌というものがあって、そこでゲーム開発会社さんがパッケージデザイナーを募集していたのを見つけたんです。私はデザイン事務所でPhotoshopとIllustratorが使えるようになっていたので、それを活かして仕事ができるなと思って応募したのですが、採用されたら、いきなりLightWaveを渡されて、「これでキャラクターのモデリングをして」と言われてしまい、これは参ったなと(笑)。
野口:2Dのデザインの仕事だと思ったら、3Dの仕事を任された(笑)。
富岡:そうなんです。でもその上司から「Photoshopに奥行きがついただけだから大丈夫だよ」と言われ、それを真に受けてやり始めたら3DCGというものの面白さに目覚めてしまって。要は、子供の頃に組んでいたプラモデル作りをパソコン上でやるようなものだったんです。それですっかりCGに魅了された私は、大学院を卒業するまでの約2年間、ずっとそこでアルバイトをしていました。
野口:就職活動はそのときの経験を売りにして臨まれた?
富岡:当時はまだ個人のパソコンでは映像のレンダリングができるスペックではなかったので、静止画の人間や風景をLightWaveで作ってポートフォリオとしていました。でも、なかなか採用してもらえなくて、十数社くらい滑りました。実はDream Pictures Studio(以下、DPS)も1回滑っているんです。そのあとポートフォリオを作り直して、「次に滑ったら諦めよう」と思って、もう一度DPSに応募したところ、「2回応募してくれた学生は初めてだ」と言われ、モデラーとして採用していただけました。
Dream Pictures Studio
1997年にソニー・コンピュータエンタテインメント、ナムコ、ポリゴン・ピクチュアズが合弁で東京・有明に設立したデジタルコンテンツスタジオ。ハリウッド作品のようなフルCG映画作りを目指したが、頓挫し1999年に解散した。
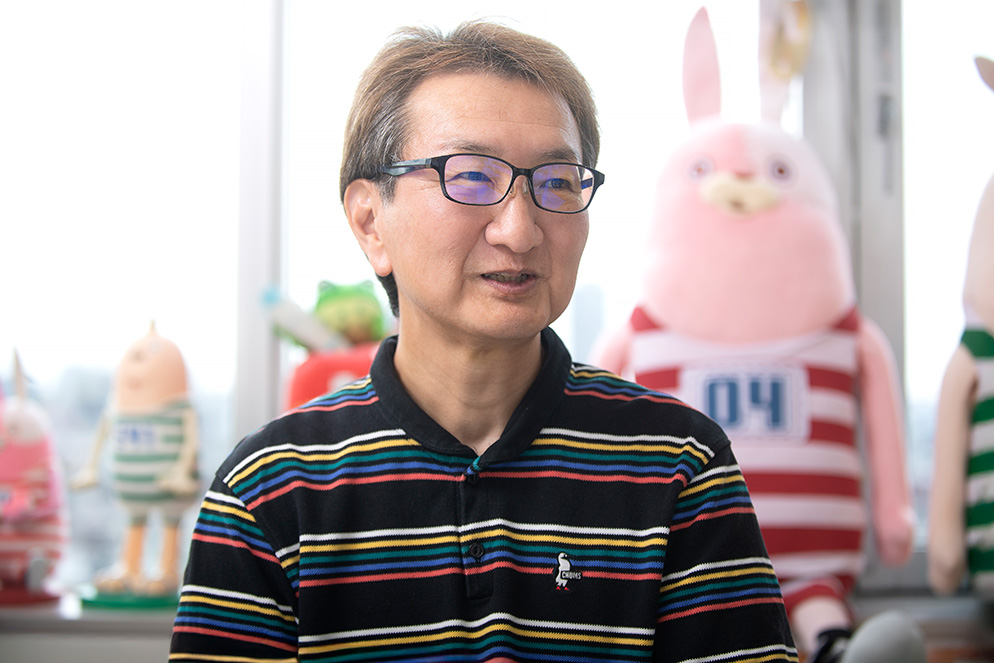
野口:DPSでは最初の頃にどんなお仕事をされていましたか?
富岡:入社して1ヶ月ぐらいでMayaのベータ版が届いたので、社内向けのマニュアル作成をしていました。当時はLightWaveの方がモデリングもレンダリングも優れているなと感じましたね。その頃になると、個人のパソコンでもある程度レンダリングが速くなっていたので、静止画だけでなくアニメーションも自分で作り始めて、それが『SiNK』に至ります。発表したのは1999年でした。
90年代末『SiNK』で注目もその裏にあった苦難とは
野口:僕が富岡さんを知ったきっかけは、『SiNK』で、当時大きな衝撃を受けました。あの作品を作っていた時の状況を教えていただけますか?
富岡:DPSで仕事をしたあと、家に帰ってから個人制作として作っていました。会社ではシリコングラフィックスのOctaneでMayaを使い、家ではLightWaveを使い、毎日がCG漬けの日々でした。期間は1年半くらいでしたが、幸せな時間でしたね。
野口:当時、日本のCG業界にはフルCG映画を制作する機運があり、スクウェアや、バンダイのデジタルエンジンプロジェクト、そしてDPSがありましたが結局、完成させることができたのはスクウェアの『ファイナルファンタジー』だけでした。DPSのようすはいかがでしたか?
富岡:DPSは東京のほかロサンゼルス・サンタモニカにも支社もあり、海外の著名なVFXアーティストも参加していました。作画のアニメーター出身の方達もいてその人達から手描きのアニメーションのノウハウを教えてもらいました。それは貴重な経験でした。実験的な試みや様々なテストは行っていたのですがフルCGの映画の実例がまだ少なく、一スタッフの私からするとプロダクションの進行の全体像まではよく分かりませんでした。

野口:僕も当時、外から見ていたのですが、「本当に完成するのかな?」と思った記憶があります。
富岡:そうですね。私が『SiNK』を作っている真っ只中の1999年の2月にDPSが閉鎖になり、退職金が出たので、翌月に一気に仕上げて、それを営業ツールにして動き出しました。『日本民間放送年鑑』という、番組制作会社の連絡先をまとめた本がありまして、そこに載っている会社に毎月100社くらいずつ「CGの映像制作ができます」という営業をかけると、5~6社ぐらいは会ってくれて、そのうちの1~2社から仕事になるんです。
野口:そのころはどんな映像を作っていたんですか?
富岡:テレビ番組のオープニングや、CMに入る前の番組ロゴ、情報番組のテキストの下で動くインターフェースとか。変わったところだと、アパレル系のお店で流れるワイヤーフレームが回る抽象的な映像も作りました。そうした15秒とか30秒の映像をLightWaveで一人で作って、毎週のように納品をしていました。そんな暮らしをしていたら、『D's Garage21』というTV番組が始まるという話が舞い込んできました。
『D's Garage21』
テレビ朝日系で1999年から2001年まで深夜に放送されていたバラエティ番組。CGやゲームなどデジタルコンテンツを公募し紹介する内容で、当時のクリエイターに大きな影響を与えた。MCは渡辺浩弐、桃井はるこほか。
野口:見ていましたよ。富岡さんの姿を初めて見たのはあの番組だったと思います。
富岡:当時、YouTubeもない時代にCG作品を多くの方に観ていただける機会はあの番組くらいしかなかったので応募したところ、番組の企画でいろいろな短編やミュージックビデオを作る機会をもらえたり、番組でフィーチャーしてくださいました。その番組の制作会社に何日も泊まらせてもらい、ミュージックビデオなどを作らせてもらえたのは良い思い出です。
野口:そんなに大変だったんですね。
富岡:TVで取り上げていただけたのはとても光栄なことで嬉しかったのですが、TVとしては仕方がないことだと思うのですが他の番組も含めて過剰な演出で紹介され、過大評価をされている気持ちになったためTV番組からは遠ざかるようになりました。

野口:富岡さんが独立したのはいつ頃になりますか?
富岡:DPSが解散してからはフリーランスとしてチームを組んでいました。当時、バンタンという学校で講師をしていたので、そこの優秀な学生や同業者の方をリクルーティングして、7~8人体制になりました。その頃は案件も大きくなり、個人の口座では取引ができない規模になったので有限会社カナバングラフィックスを設立しました。それが2004年のことでした。
オリジナルアニメ制作と海外への視野
野口:最近のお仕事としてはどんな作品がありますか?
富岡:最近多いのはゲームのルックデベロップメントですね。日本のゲームパブリッシャーさんから、「海外に通用しつつ、でも日本のマーケットを押さえたルックを開発したい」というご相談をいただいて、そういったキャラクターのデザインやCGモデルの制作を当社で行なったり、ゲームのドラマパートのムービーの絵コンテも描かせていただいてます。他にもゲームのPVなどが多いです。アニメの方は原作をお預かりして脚本、あるいは絵コンテから担当する仕事をしています。
野口:最近の傾向はいかがでしょうか?
富岡:最近、弊社の方にくる相談として、ゲームをアニメ化したいというお話が増えてきています。その場合、マンガや小説と違い、映像にそのまま持っていけるストーリーがないので、ゲームの設定をベースにこちらでストーリーを作り、脚本・絵コンテに落とし込みます。このあたりはオリジナルアニメを作ってきたノウハウが生かせられるかなと思います。そういったクライアントワークと並行して、オリジナルアニメ制作の事業も継続しているのですが、どうしてもマーケティングや出資社集めなど、営業にかける期間がとても長く、あまりハイペースに作れてはおりません。
野口:カナバングラフィックスの興味深いところは、『ウサビッチ』や『イナズマデリバリー』など、オリジナル作品を作り続けていることです。これにはどんな理由が?
富岡:DPSでもオリジナルアニメを作っていましたし、自分が20代の頃は周りにもオリジナルのCGアニメを作ってる方が大勢いたので、特に珍しいとは思わないんです。ピクサーなど海外のスタジオもオリジナル企画を作り、それを出資者に見せて作るのが一般的です。世界的にはこうした製作体制が主流で、原作を借りてくる日本の作り方のほうが特殊なのではないかと思います。
野口:海外のビジネス事情なども参考にされたりしていますか?
富岡:法人化前から一緒に仕事をしているアートディレクターの宮崎あぐりさんがブラジルのCGプロダクションと仕事をした際の話を伺いました。そのプロダクションでは毎年社長がアニメの企画を作って、それをテレビ局に権利ごと売りに行くケースもあるそうです。それで制作費を確保して、あとは創り手がしたいように作るという。日本のアニメ業界の常識とは違うビジネスもあるのだと驚かされました。
野口:原作ありきの日本の制作体制とは大きく様相が異なりますね。
富岡:弊社オリジナルの『イナズマデリバリー』は製作委員会にも入っているのですが、やはり著作権を持つからにはビジネスにおいても責任を持つことであると実感しました。委員会の方たちと一緒に日本全国のLOFTやヴィレッジヴァンガードに営業しに行ったり、監督としてサイン会に出たり、着ぐるみのグリーティングイベントのときはビラ配りまで行ないました(笑)。

野口:プロデューサー業と監督業、さらに現場の仕事までこなしておられると、どれだけ時間があっても足りなそうですね。
富岡:全部自分でやらなければといけないと思ってしまって。実際、大変です(笑)。なので、難しいコンテの仕事は自分で描きつつも、オーソドックスな内容であれば最近は社内のスタッフに任せるようにしています。最初は私のラフを清書してもらって、次は脚本からコンテに落とし込んだものにフィードバックをするなどして、なるべく描ける人を増やしていこうと動いています。クライアントの窓口も私だけではなくディレクタークラスが対応できるよう教育をしています。
野口:お仕事においては海外も視野に入れているそうですね。
富岡:毎年9月から東京都の支援制度として「海外進出ステップアップセミナー」という講座がありまして、そこでは海外のフィルムマーケットでピッチ(プレゼン)をするときのノウハウなどを教えてもらえるんです。そのカリキュラムのなかでは自分たちの企画も作ることができます。審査に通るとフランスのアヌシーで行われる、MIFAという巨大なアニメーションフィルムマーケットに出展ができて、そこでものすごい数の商談を繰り返すんです。日本ではいつの間にか子供向けのアニメがとても少なくなっていましたが、海外は子供向けのアニメがやっぱり多いですね。最終的な目標としては、私が引退してもこの会社で作り続けられるグローバルな作品を残したいんです。
オリジナル企画の作り方と、挑む上での責任
野口:富岡さんは専門学校などで先生もされていましたが、オリジナル企画やストーリーなどの作り方はどのように教えられているのでしょうか?
富岡:脚本の書き方の本のほとんどに同様な説明があるのですが、最初に「ログライン」を作ります。これは作品の内容を4~5行で示した短い文章です。ハリウッドの企画書は非常に分厚いので、プロデューサーが読んですぐにジャッジできるよう短い文量で人を惹きつける必要があります。私の場合はそれにプラスして1枚のコンセプトアートを付けてストックしてあります。これを企画の原案とし、まずキャラクターを掘り下げて設定を作ります。海外のピッチだと作品のバリューの説明や、「その作品を見ると何が得られるのか」などを書く必要があり、そのあと数話分ストーリーを作って、企画書が出来上がります。これが私が学び、教えているオリジナル企画の作り方です。
野口:カナバングラフィックスの社員の方にもそういったものを定期的に教えていたり、オリジナル企画の原案を募集したりは?
富岡:募集という形ではありませんが、最近やっと私のように会社勤めをしながらオリジナルアニメを作った若い社員が出てきています。あとは、漫画の読み切りを描いて雑誌に載ったディレクターがいたりと、自分で作ってみようかなという雰囲気がやっと社内に現れてきました。もうちょっとそのようなことに取り組む人数が増えたり、更に高いレベルを目指してくれると嬉しいなと思います。
野口:CG業界でも一時オリジナル企画を立ち上げようとした時期がありましたが、なかなか上手くいきませんでした。カナバングラフィックスの作り方が突破口になれば良いなと思います。
富岡:よく、プロデューサーやクリエイター、経営者の方が相談しに来るんですけど、単にオリジナル作品を作りたいのか、ビジネスをやりたいのか。権利を持つということはビジネスの責任を取るということでもあるので、出資してくださる方たちにちゃんとお金を返す努力をする必要があります。ただ「作りたい」のであればそれはオススメしないし、逆にビジネスをやりたいのであれば、しっかりとしたマーケティングを最初に始めることをお勧めします。
野口:目的がハッキリしていないまま、どっちつかずになってしまいますね。
富岡:今はグローバルに配信・放送の権利を売り、国内では商品化とコラボで回収するケースが多いようです。以前、Kidscreenというフィルムマーケットに参加してから毎月Kidscreenの雑誌が送られてきます。そこには日本では目にしないような数多くの作品が紹介されています。それらをリサーチして視聴が可能な作品は視聴し、レビューを見てどのような作品性が評価されているのか、またどのような層に人気があるのかを調べます。海外ではディストリビューター(番組の放送と配信の権利を売る代理店)の力が強いのでディストリビューター側の意見をよく聞き、彼らが好む作品を意識します。ただ、あまりに彼らの言う通りに作品を仕上げると凡庸な作品にもなってしまうのでバランスが難しいところがあります。商品化については日本全国の小売店を回り、今の売り場で人気のあるキャラクターや商材を調べていきます。店舗で実際に見るとウサビッチの頃には売っていなかった新しいタイプの商材を発見することも多くあります。店長さんや店員さんの意見もとても参考になります。売り場はキャラクターのブランディングの場でもありますので売り場から作品が知られていく相乗効果もあります。
作品が軌道にのると飲食やイベントと絡めてコラボが出来るようになりますと、その期間中にポップアップの売り場を作り、そこでしか買えないグッズを販売します。ただ、その段階で既にある程度の数のファンがついていないと難しいです。
野口:富岡さんは若い頃に月100社アタックしているわけですからね。
富岡:今でも年間にすると250社くらいは営業しています。最近は社員も営業を手伝ってくれますので助かっています。でもそれって、誰でもできることなんですよ。
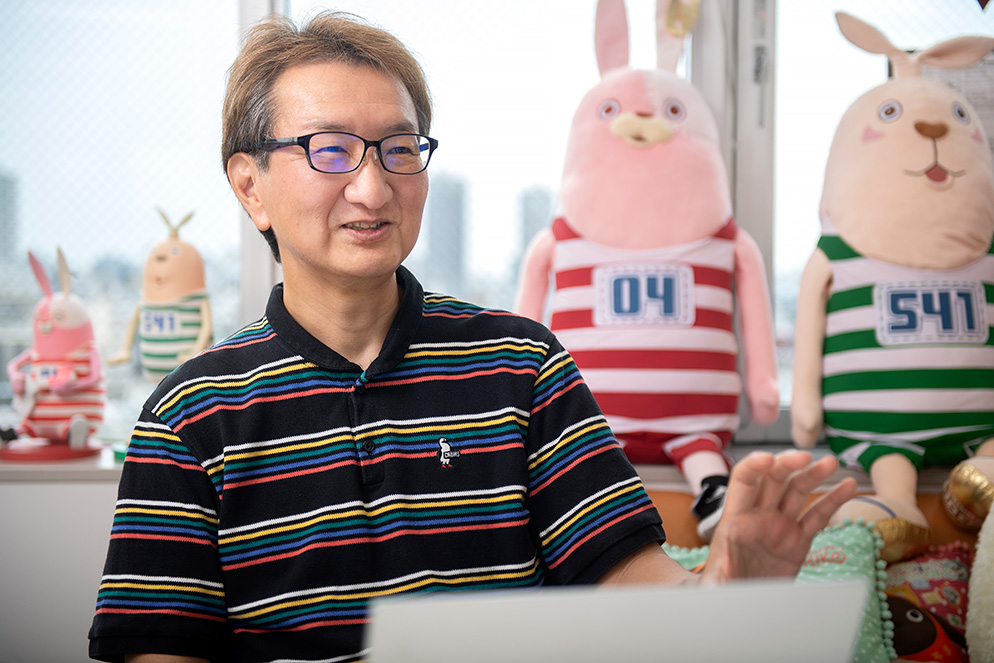
マネジメントとクリエイターの両立に朝活まで週7日間のハードワーク
野口:AIについての取り組みはどのようにされていますか?
富岡:AIのセミナーとかに興味があって行くんですけど、私が興味があるのがFlow PTの管理とかマネジメントの領域なんですよね。データベースの数値をデザイナーが入力している時間がもったいなくて。あと、ロイヤリティの計算や経理といった、バックオフィスとかマネジメントの一部をAIがやってくれたり、そういうツールを誰か作ってくれる人がいないかなと思っています。
野口:今は制作のスタッフが足りていなくて、本来的には管理する仕事にも拘らず、その人たちを管理する必要がある現場です。それよりも優秀な制作スタッフとサポートAIがあればいい状況を作って、それでできた余裕でアーティストを雇いたいですね。
富岡:確かに。そのほうがビジネスとして広がりそうな感じがします。皆さんは生成AIに興味津々のようですが、どちらかというと、人間が面倒くさいと思う作業にこそAIが来てほしいなと私個人は思います。

野口:現在、富岡さんの中で経営者としての仕事の割合と監督としての仕事の割合はどのぐらいでしょうか?
富岡:経営の負荷が大きいです。何作品か抱えてるので、強制的に火曜日と木曜日だけは絵コンテと脚本を書く日にして、その日はなるべく私に声をかけないように社員にお願いしています。残りの月・水・金曜日は社長、営業、マネジメント業をしています。あとは土日も絵コンテや脚本を書いています。
野口:働き過ぎでは?(笑)
富岡:そうなんですけど、火曜木曜はメールの処理も行なう必要があって、そうでもしないと終わらなくて。あと、朝活では英語とBlenderとウェブトゥーンの勉強をしています。
野口:ウェブトゥーンまで描いているんですか!
富岡:また昔に戻って漫画家を志そうと(笑)。要は、いきなり企画書を作って「出資してください」と言っても、なかなか通らず、「やっぱり原作がないと」という話になっちゃうので。であれば原作に該当するものを自分で描いてXとかで何作品か試しに投稿してその実績としようと。SNSでヒットしているキャラクター達も個人作家の方達が複数のキャラクター作品を出して、その中で伸びたものに労力を注いでいます。私は3作品描いていて、2作品は昔ながらの紙とアナログで、残りの1作品はCLIP STUDIOを使いながらフルカラーで描いています。
野口:先ほど引退のお話もありましたが、富岡さんが働けば働くほどそれが遠のいていきますね。
富岡:自分自身がボトルネックになって会社の新しい活動が遅れることも時々あります。社員に任せられるところは任せるようにし始めていますがその範囲をもっと広げなければなりません。今は海外からのお仕事が増えつつあり、またオリジナルIPも少しづつ前進しています。初動は私がまだ頑張らなければなりませんが、軌道にのれば社員に譲渡していきたいと考えています。これから約10年をタイムリミットとして、後継の人材を育てるか親会社を見つけて経営者を交代するか、その両面で考えています。

富岡 聡氏
とみおか さとし。ディレクター、有限会社カナバングラフィックス代表取締役。
1997年、東京農工大学大学院修了後、株式会社Dream Pictures Studio入社。1999年にフリーランスのデザイナーとして活動を始め、個人制作の初のオリジナルアニメーション『SiNK』を発表。2004年、有限会社カナバングラフィックス設立。2006年、監督、脚本、絵コンテを担当した『ウサビッチ』の放送・配信を開始。監督作品として、『イナズマデリバリー』(2017年)、『ふしぎ駄菓子屋銭天堂』(2020年~2022年3月放送まで) などを制作する。
2002年度文化庁芸術祭優秀賞を受賞。
https://www.kanaban.com
フィルモグラフィー
1999 『SinK』 監督・原作・脚本・絵コンテ・デザイン・美術設定・CG制作
2000~2003 監督作品 ショートフィルム『Coin Laundry XYZ』、『SMA STATION スノッビーズ』、『ガスタンクマニア』、『ジャスティスランナーズ』、『Smap Short Films Game Shingo』、ミュージックビデオ『MASTER MIND』、PV『メンタンピンタワレコ』
2004 『だめじゃない2004 -富岡聡仕事集1999-2003-』作品集DVD、監督・演出担当・ゲームPV『EXIT』、広告『キックおでん』、『ヨーロッパHONDA OK Factory』
2005 監督・演出担当・CM『サントリーバブルマンシリーズ』、遊技機やゲームムービーのモデリングやCGアニメーション演出多数。
2006~2010 『ウサビッチ』 監督・絵コンテ
2011~2024 CM、遊技機、ゲームムービーCGアニメーション演出多数。2017 『イナズマデリバリー』 監督・絵コンテ・原案
2020 『ふしぎ駄菓子屋銭天堂』(022年3月放送まで) 監督・絵コンテ
2024 『第五人格ショートアニメーションARNOLD&PUPPETS』監督・脚本・絵コンテ
Supported by Enhanced Endorphin
INTERVIEWER :野口光一(東映アニメーション)
EDIT :日詰明嘉
PHOTO :弘田充
LOCATION :カナバングラフィックス







