トレンド&テクノロジー / デジタルコンテンツの未来〜温故知新〜
第12回:野﨑 宏二(VFXスーパーバイザー/株式会社N-DESIGN代表取締役)
- アニメ
- コラム
- モーションキャプチャー
- 映画・TV

CGと縁の深い方々にお話をうかがい、デジタルコンテンツの未来を見通していく記事をお届けする本連載。今回はVFXスーパーバイザーで
株式会社N-DESIGN創業者である野﨑宏二氏に登場していただいた。宇多田ヒカルのミュージックビデオや『CASSHERN』 ほか、20年以上に渡って邦画の大型タイトルに多数携わるN-DESIGNと野﨑氏。それらの監督との仕事を通じて経験したさまざまなエピソードやVFXスーパーバイザーの仕事の要点、会社組織としての発展と哲学についてたっぷりと語っていただいた。
【聞き手:野口光一(東映アニメーション)】
Supported by EnhancedEndorphin
学生時代から講師を務め、20代でN-DESIGNを設立
東映アニメーション/野口光一(以下、野口):まずは野﨑さんのCGとの出会いから伺えればと思います。
野﨑宏二(以下、野﨑):僕は粘土細工などが好きで、美術系の高校から美大の彫刻科を志望していたのですが、受験を掛け持ちするなかで東京造形大学で新たに造形計画科という学科ができることを知りました。それがCGを専攻するコースだったんです。結果的にCGの方に進んだのですが、彫刻を勉強していたおかげで、3D的なモデリング能力には後々役立ったと思っています。
野﨑:初めて使ったCGソフトは何でしたか?
野﨑:Prismsでした。最初の1、2年目はまだ大学側も手探りでMacを中心に教えていたと思いますが、3年次にSilicon GraphicsのIndyなどが導入されたように記憶しています。ゼミは吉田健治先生でした。当時、CG業界はまさに変革の時代でしたね。CG・VRの研究開発会社VSL(ビジュアルサイエンス研究所)ができて、そこからデジタルハリウッドなどいくつもの会社が作られました。
野口:野﨑さんもデジタルハリウッドの設立時に少し関わられたそうですが?
野﨑:現在も校長をされてる杉山(知之)先生が設立前には造形大で非常勤講師をされていたんです。その繋がりもあって僕も4年生の時に講師のような形でお手伝いをしました。カリキュラムもまだできていない状況で、僕は第一期生のTA(ティーチングアシスタント)を務め、2年目ぐらいまではPrismsを教えていました。御茶ノ水にあったVSLの隣の一角に教室を作り、30台ほどのIndyでスタートしたのがデジタルハリウッドの初期だったと思います。
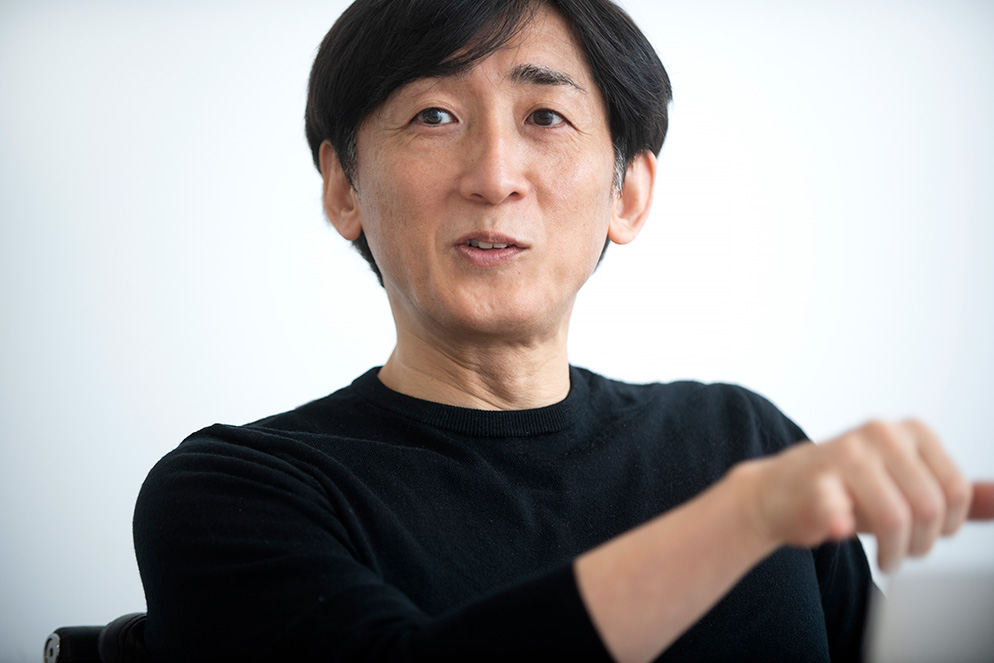
野口:大学4年でTAをされて、就職活動は?
野﨑:就職活動はしませんでした。デジタルハリウッドの施設を24時間自由に使える状態だったので、4年生の時はTAをしながら裏でずっと作品を作ってNICOGRAPH学生コンペなどに出していました。そうしたら吉田先生にそのままVSLで働かないかと誘って頂きまして、大変迷いましたが、そのときアルバイトながらすでにVSLの仕事をこなしていたのもあり、フリーランスとしてやっていくことにしたんです。なので、VSLには正社員として入らず、同じく吉田先生が立ち上げたばかりのデジタルクリエイター専門の派遣会社のデジタルスケープを経由して、VSLで派遣社員として働くことにしました。実は僕がそこの第一号登録者なんです。たぶんそんな記録は残っていないと思いますが(笑)。
野口:その頃のVSLがどんな様子だったか教えていただけますか?
野﨑:僕が入った頃のVSLはデザイナーが20人ぐらいいて、いろんなことをやっていましたね。最初はPrismsを使っていましたが、会社全体ではその頃メインで使用するソフトがSoftimageに変わりました。VSLは日本で初めてモーションキャプチャーを導入したグループの一つでもあります。吉田先生はビジネスパーソンとしても先見の明がある方で、他にも展示会映像のデジタルアミューズ、ゲーム会社のポリゴンマジック、WebプロダクションのIMJなど色々なことを手がけて、どんどん規模を大きくしていました。
野口:野﨑さんはその後、ご自身で会社を設立されるわけですが、どのタイミングでしたか?
野﨑:社会人として5年目の頃でした。元々会社を立ち上げようと思っていたわけではなかったんです。ただ、フリーランスとして仕事を受けていくと、とても一人ではこなせないような規模になっていってしまい、同時に3~4本受けるようになったときにアシスタントを使うようになりました。最初は自宅のリビングが作業場でしたが、アシスタントが増えて手狭になると、近くに10畳ぐらいのワンルームを借りて、5人ぐらいの規模になったときにN-DESIGNを設立したかたちです。それが2001年の5月1日のことでした。
野口:どんなスタッフが集まっていましたか?
野﨑:阪上(和也氏:現取締役)はVSLの同期で、藤田(卓也氏:現取締役)も経歴で言うとその1年後輩。やっぱりVSL時代に知り合った人に手伝ってもらって創業した形ですね。
野口:当時はマシンも高価で気軽に買えなかったと思いますが、フリーランスになってからはどうされていましたか?
野﨑:常駐先で作業することもありましたし、フリーになって3年目ぐらいの時に、ようやくDellのワークステーションが40~50万円ぐらいで買えるようになったので、自分で購入して自宅で作業したりしていました。途中からは高すぎると感じて、秋葉原で自作PCを作るようになりましたね。

『CASSHERN』紀里谷監督の斬新な制作スタイル
野口:会社設立前後は、どのような案件が多かったですか?
野﨑:ミュージックビデオやCM、TV番組のオープニングタイトルなど、本当に何でもやっていましたね。音楽アーティストのプロモーション映像や、VSLで受けていた格闘ゲーム『DEAD OR ALIVE』シリーズなども並行していました。あとは『HOT WHEELS』というアメリカのミニカーが変形するロボット『ROBO WHEELS』のプロモーションビデオとか、とにかく無茶苦茶働いていました。僕が一人でやってる時はジェネラリストでやったんですけど、アシスタントが入るようになってからは、テクスチャーを描いたりアニメーション制作するところなどは彼らに任せ、僕は得意なモデリングやコンポジットなどに集中し、分業を進めて行きました。
野口:その頃、宇多田ヒカルさんのミュージックビデオで一躍注目を集めました。
野﨑:それまでの様々なミュージックビデオの繋がりから、突然この話が転がり込んできたんです。会社を立ち上げて2年目ぐらいだったと思います。紀里谷(和明)監督との出会いもその時でした。最初は『traveling』で、その後『SAKURAドロップス』など5作品でVFXスーパーバイザーを担当しました。
野口:そのお仕事から映画『CASSHERN』に繋がっていくのですね。
野﨑:そうですね。何本かミュージックビデオを作っているうちに、監督が「実は映画をやりたいんだよね」という話をしてくださり、一緒にやることになりました。
野口:『CASSHERN』の作業ボリュームは相当なものだったと思いますが、自信があって臨まれたんですか?
野﨑:ただただ若いときの勢いでしたね(笑)。紀里谷監督は、とても斬新な考えを持っていて、ストーリーとか自分がやりたいことは一切削りたくないという一方で、僕らがプリビズで作ったテクスチャも貼ってもいないようなラフな映像を「これは斬新で格好良いね」みたいにおっしゃる。リアルであることを至上とせず、デザインセンスで画を作ろうと。ディティールを詰め込むことが良い画になるわけじゃないという発想で、「なんならCGではなく手描きアニメでも良いんじゃない?」といった話までされていました。僕はCG会社なんですけど……って(笑)。そのくらい柔軟な考えの監督でした。
野口:CG制作会社としては困ったものですね(笑)。
野﨑:そうなんです(笑)。さらに画質については多少落としても構わないと言うんです。なんなら画面を荒らしたいと。時間とお金がかかるのはレンダリングなので、それは大いに助かりました。もちろん撮り切り(画面全体に被写体が映っている状態)に近いようなところは、HDのサイズで納品していますが、フルCGのところはほとんどをハーフサイズでレンダリングしてブローアップしていました。そうすればレンダリング時間が4分の1になるので、その分、他に作業をあてようという考えでしたね。

野口:制作当時、何人くらいスタッフがいましたか?
野﨑:制作管理含めて多い時で25人ぐらいでした。そのなかには専門学生のインターンもいて、後に入社した人もいます。弊社の制作部長の川瀬(基之)もその中の一人です。ちなみに、『CASSHERN』のCG制作は制作プロダクションが部屋を借りてくれて、クランクインまでは監督たちがいるスタッフルームとして機能し、実写のクランクアップをしたらそこにCGチームが入っていく形でした。CGの機材もMayaとかAfter Effectsなどのソフトをハードも込みで20台ぶんぐらい用意してもらえました。
野口:実際、『CASSHERN』の制作はどれくらいの期間でしたか?
野﨑:撮影期間を含めると1年ぐらいかかったと思いますが、仕上げは6ヶ月ぐらいだったと思います。当時、『CASSHERN』、『キューティーハニー』、『デビルマン』、『鉄人28号』など、同時期にマンガやアニメ原作の実写+CG映画が発表される中、『CASSHERN』が一番最初の公開予定で(2004年4月)、監督はとにかくそこに間に合わせることを戦略的に重視していました。公開が後ろに回ればそれだけ話題性が薄れるとの考えだと思います。デザイナーとしては時間をかけてもっとクオリティを上げたい気持ちでいましたが、監督は「クオリティを落としてるんじゃない。これがいいんだ」と言って僕たちを導いてくれましたね。
『20世紀少年』堤監督によるテレビ由来の演出手法
野口:VFXに特化して仕事をするようになったのは?
野﨑:仕事のつながりの流れでそうなったと言えます。最初の頃は先ほどの『DEAD OR ALIVE 3』(2002)など、フルCG系のゲームムービーや『ROBO WHEELS』などを制作していましたが、ミュージックビデオの流れで実写作品の方も手伝うようになって、VFXの仕事が増えていきました。
野口:『20世紀少年』シリーズなど堤幸彦監督とのお仕事も長いですが、最初の出会いは?
野﨑:『CASSHERN』の2~3年後ぐらいに、映画『サイレン~FORBIDDEN SIREN』(2006) で呼ばれたのが堤監督との出会いです。当時、堤監督はずっと同じチームで仕事をされていたのですが、ラインプロデューサーが「一度スタッフを総入れ替えしてみてはどうか」と提案したそうです。それで、撮影部以外が総入れ替えとなって、CGも新しいところに声をかけようということで、僕たちに話が来ました。堤さんは当初、新しいチームで作ることを渋っていたそうですが、結果的にその時のチームを気に入ってもらえて、僕らも10年以上、一緒にお仕事をするようになりました。
野口:堤監督の演出スタイルは独特だと聞きますが。
野﨑:ええ、堤さんは現場の近くにテントを張ってブースを作り、そこからマイク越しで現場に指示を出すスタイルですね。

野口:普通、監督というのはカメラの横にいて直接演技指導する場合や、モニターの横に張り付いて演技指導をするときだけ役者のもとに行くわけですが。
野﨑:これは堤さんがテレビ業界出身の方だからだと思います。昔、とんねるずさんなどとバラエティ番組をずっとやられていた方で、秋元康さんとも先輩後輩の仲で、秋元さんの本を堤さんが演出されていたり、ショートコントなどを作っていたと聞いています。そこで培ったテレビ的な手法を映画業界にもどんどん採用したんだと思います。なので、僕は基本的に監督のそばで、画面を見ながら「この辺こうしたいんだけど」というアイデアを聞いて、それを撮影部や照明部に伝えるのが現場での役割でした。堤監督はテレビ業界らしくインスピレーションで指示を出すことが多いのですが、それをやることによって後々のVFXがより面倒なことになるリスクがあったり、予算が変わってくる部分もあるので、それをどう具現化していくか、即断即決が求められます。撮影の流れを止めるわけにはいきませんし、現場とは常にかけ引きする必要がありましたね。
野口:コンテは事前に用意されていましたか?
野﨑:はい。CGが多くなるような重要なシーンは事前にコンテを作ります。ただ、堤監督は話に全く関係ないキャラクターを突然登場させたりするんですよ。『トリック』を見てもらえればわかると思いますが、ガッツ石松が変な生き物になって飛んでいたりとか。台本にないことを現場でいきなり説明して、役者さんやスタッフを困らせることもありましたね(笑)。逆に、紀里谷監督は『GOEMON』の時は撮影にインする前の段階で、ほぼビデオコンテで2時間半の映画が出来上がっているような状態でして、撮りながら素材を入れ替えていくような作業でした。アニメーションを作っているような感覚でしたね。2008年頃だったと思いますが、撮影前に主要なシーンのモーションキャプチャーを撮ってプリビズを作ってからに現場に入りました。そして、現場が終わったら今度は本番用にもう一度モーションキャプチャーを撮ってCGを仕上げるという形で、贅沢に2回キャプチャーを撮っていました。
野口:そうした現場を重ねる中でVFXが認められてきたという感覚はありましたか?
野﨑:堤監督や紀里谷監督は最初から現場とVFXに対する垣根がありませんでしたね。特に『GOEMON』や『20世紀少年』の場合は「VFXありきなんで、コンテを含め仕切りをお願いします」という雰囲気でした。アクションシーンとか、僕らがプリビズを作らないと現場は誰も設計図が分からないから、全部署が「プリビズ待ちです」みたいな感じで。堤監督に至っては、僕たちがカメラのデータを持ち出すと、「好きなようにやって」と言っていなくなったり(笑)。当時にしては、かなり柔軟にカメラを回せる環境だったと思います。
『Diner ダイナー』のクリーチャー制作
野口:今、メインで使っているソフトは何ですか?
野﨑:MayaとNukeがメインですね。Houdiniもエフェクトで使っています。
野口:レンダラーは結構変えていますか?
野﨑:結果的に色々変えましたね。業界のトレンドもありますし、周りの意見を聞きながら決めることもあります。

野口:今はArnoldがメインですか?
野﨑:はい。GPUレンダリングはまだですが、試したいですね。
野口:クラウドレンダリングサービスも使っていますか?
野﨑:正確ではないですが5年前くらいから使っていると思います。自社では100数十台のサーバーを持っていますが、電気容量の問題もあり、これ以上台数を増やすことはできないので、繁忙期は外部のサービスに頼る形になっています。
野口:2019年の映画『Diner ダイナー』ではVFXの犬がリアルでしたね。日本もCG動物ができるという業界の指標にもなったのかと思いました。生物やクリーチャーの制作はどのようにされていますか?
野﨑:うちでは特定のキャラクター専門の担当者は置いていません。本当に必要な時は、フリーランスの方に応援をお願いしたりします。例えば、元イメージエンジンの清水雄太さんのような方にもご協力いただくことがあります。長い間お付き合いのある方で、色々と相談させてもらっています。スポットでアドバイスをいただくこともあれば、ショットの中で人手が足りない時に、清水さんの周りのフリーランスの人を紹介してもらうこともありました。
野口:筋肉のシミュレーションもされていますか?
野﨑:はい。筋肉からシミュレーションしています。ただ、最近思うのは、筋肉自体の動きは盛り上がりくらいで、思ったほど効果がないということです。むしろスキンスライド、つまり表面の皮がよれたりすることの方が視覚的に分かりやすく、シミュレーションの効果が大きいと感じます。もちろん、筋肉あってのスキンなのですが……。
野口:骨から筋肉、皮膚と作って、毛を生やすまできちんと作っているのですか?
野﨑:真面目にやるとそうなってしまいますね。シミュレーションも当然行いますが、効果が薄いと感じることもあるので、キーフレーム単位でアニメーターがスカルプトしたりもします。それって、もはやアニメーションのセンスであって、シミュレーションではないような気もします。
野口:野﨑さんの彫刻の勉強は、造形という意味でこのような制作に活きているのではないでしょうか?
野﨑:僕自身がモデリングなどの作業をしたりするわけではないのですが、見る目としては活きていると思います。 どんな役割であっても、どんな手法を使っても、最終的には監督が望む映像さえ出来上がればいいので、自分の目とセンスを信じるしかないですね。
野口:そういうところを教えられるのは現場仕事でないと伝えづらいものがありますよね。
野﨑:そうですね。監督が何を求めているかを汲み取れるかどうかが、VFXスーパーバイザーの適性になりますかね。例えば紀里谷監督のように、ディテールよりもカッコよさを追求する監督の場合、時間をかけてすごいカットを作っても、「これを何百カットも作れます?」と言われて「せいぜい10カットです」となれば「この10分の1のディテールでいいので魅せ方を工夫して100カット作って」となったりします。求められているものが人によって全く違う、ということはよくありますね。
VFXスーパーバイザーの育成と社内分業化のねらい
野口:現在エヌデザインでは野﨑さん以外に何人もVFXスーパーバイザーがいますが、やはり意識的に育ててこられたのでしょうか?
野﨑:はい。それは意識的に行なっています。自分が何かをして育てたというよりは、何年に一度、ポンとそういうことに向いている人が現れて、一緒に現場にいる中で自然と育っていくという感覚ですね。
野口:現在、何人くらいのスーパーバイザーが育っていますか?
野﨑:朝倉(怜氏:合成部長)や阪上(和也氏:デザイン室部長)、名取(蒼史氏:デザイン室部長)、柴(亜佳里氏)、そして最近では8月に公開される『隣のステラ』という映画でスーパーバイザーデビューする藤原(芽生氏)という女性もいます。
野口:VFX会社でこれほど多くのスーパーバイザーがいるのは珍しいですね。
野﨑:そうですね。今やウチのエースである朝倉は、白石和彌監督の作品なども手伝わせてもらっています。最近ではNetflixの『極悪女王』も弊社が担当させていただきました。
野口:現場に出るとなると、監督と直接の遣り取りが発生するので難しいのでは?
野﨑:そうですね。監督との相性もありますし。

野口:VFXスーパーバイザーの難しいところは、純粋な技術だけでなく監督やカメラマンとのコミュニケーションが求められるところなんですよね。言われたことを全てYESとしてしまうと仕上げ作業が回らない。スーパーバイザーは「これはこうでないとダメです」と言わなければいけないですから。
野﨑:『隣のステラ』は若い女性監督(松本花奈)だったので、僕のようなベテランが行くよりも、若い感性の女性同士で作り上げていくほうが良いと考え、藤原に入ってもらいました。長く映画業界で付き合っていくのであれば、彼女がその関係値を作るほうが意味のあることだと思います。
野口:『隣のステラ』は何カットくらいでしたか?
野﨑:100カットくらいはあったと思います。デビューには、ちょうどいい規模でしたね。VFXシーンも、星空合成やバレもの消去、フレアー追加など、細かい作業が中心でした。現場にもなるべく一人で行ってもらいました。
野口:その作品では、野﨑さんはプロデューサーという立場になる?
野﨑:そうですね。なるべく口出ししないように心掛けました。でも、どうしても口を出したくなるんです(笑)
野口:『CASSHERN』の後、少数精鋭でいくか、大規模な分業にするかで悩まれたとのことですが、今はどうお考えですか?
野﨑:難しい問題ですが、今は少し規模を大きくする方向で舵を切っています。ジェネラリストをベースに案件を回すことの一番のリスクは、人に依存しすぎることです。これまで頼っていた人がいなくなると、問題になることが多かったので。いかにリスクを減らすかは常に考えています。
野口:今は緩やかな分業といった感じでしょうか?
野﨑:分業の色が濃いですかね。モデラー、セットアップ、アニメーター、エフェクト、コンポジット、それぞれ専門に分かれています。ショットやレイアウトを担当することになれば、アニメーターやモデラーが束になって皆で協力し合うこともあります。ジェネラリスト的な仕事は、本当に1割か2割くらいだと思います。
野口:採用の段階で細かく職種を分けている形ですか?
野﨑:最初はみんなに一通りやらせます。半年間アニメーションチームで仕事をさせたり、モデリングの仕事をさせたりするうちに、「君はモデラーに向いているかな」、「アニメーションに向いているかな」という感じで振り分けられます。その中でたまに「全部やりたいです」という人がいるので、「じゃあ、ジェネラリストとして頑張って」という感じですね。
野口:学校から来る人は、ポートフォリオがアニメーション中心ですよね。それでも全てを一度やらせてみるんですね。
野﨑:そうですね。僕自身がだいぶ教育事業もしてきた側なので、言いにくい話ではありますが、学生時代に覚えたスキルや技術レベルは、そこまで大したことはないんです。現場に入ればすぐ追い抜けるものですから。それに、たとえモデリング志望で入った子でも、モデラー以外の可能性も探るために、一通りやらせてみます。本人が気づいていない才能があるかもしれませんし。学生で1年ほどやっているレベルだと、自分が何に向いているかなんてまだ分からないと思いますから、可能性を潰すのはもったいない、という思いもあります。
野口:制作進行の採用についてはいかがですか?
野﨑:弊社ではお金の管理も含めたラインプロデューサーに近い人間は4人で、専業でプロダクション・マネジメントをしているのは2人です。
野口:どんな人が入ってきますか?
野﨑:よく言われる、デザイナーを目指していたけど、途中で制作に転向したという人は弊社にはいなくて、最初からマネージメントがやりたいという人が多いですね。そういえば、助監督経験者にマネジメントをしてもらうと現場の仕切りやカットの流れも分かっているので助かるという話を他社から聞いたことがありますね。
野口:AI技術の導入についてはどうお考えですか?
野﨑:僕はこの流れは逃げられないと思っています。NukeにもAI機能はありますし、消しゴム機能もAIですよね。これからはVFX業界でも普通に認められてくると思います。僕たちの最大のライバルはAIでしょうね。そう遠くない未来に、本当に人がいらなくなる時代が来るだろうなと。楽になるということは、人がいらなくなるということですから、ウチのスタッフにもAIを含めた「新しいスキルを見つけないと仕事がなくなるぞ」、と伝えています。マスク切り、バレ消しといった作業から、どんどんAI頼りになるでしょうね。
野口:それでも職人でないと出来ない仕事もありますよね。
野﨑:はい、細かい詰め作業は、優秀な人間でないと全然ダメだと思います。でも、その途中までは大部分が自動化されるでしょうね。それに、ディレクション的な仕事もかなりAIに取られると思います。この業界に限った話ではありませんが、これからはいかにAIを利用しながらモノを作れるかが問われると思います。

野﨑 宏二氏
のざき こうじ。株式会社エヌ・デザイン 代表取締役社長/VFXスーパーバイザー。
1973年、岡山県生まれ。CGデザイナー・ディレクターとして活動した後、2001年に「エヌ・デザイン」設立。映画、ミュージックビデオ、ゲームムービー等、多方面でCGディレクター/VFXスーパーバイザーとして活動する一方、ショートムービーやミュージックビデオ等で監督としても活動中。目標は映画の本編を監督すること。最近では漫画家としても活動中。
一般社団法人VFX-JAPAN監事。
LINEマンガより「プラントハンター」が6月27日より連載開始。
https://manga.line.me/product/periodic?id=S152316
■フィルモグラフィー
2004『CASSHERN』 VFXスーパーバイザー
2005『鉄人28号』 プロダクションスーパーバイザー
2006『シムソンズ』 VFXスーパーバイザー
2006『サイレン~FORBIDDEN SIREN』 VFXスーパーバイザー
2007『キサラギ』 VFXスーパーバイザー
2007『包帯クラブ』 VFXスーパーバイザー
2007『自虐の詩』 VFXスーパーバイザー
2008『銀幕版 スシ王子!~ニューヨークへ行く』 VFXスーパーバイザー
2008『20世紀少年 第一章:終わりの始まり』 VFXスーパーバイザー
2009『20世紀少年 第二章:最後の希望』 VFXスーパーバイザー
2009『20世紀少年 最終章:僕らの旗』 VFXスーパーバイザー
2009『GOEMON』 VFXスーパーバイザー
2009『守護天使』 VFXスーパーバイザー
2010『劇場版TRICK 霊能力者バトルロイヤル』 VFXスーパーバイザー
2010『さらば愛しの大統領』 VFX監修
2011『はやぶさ/HAYABUSA』 VFXスーパーバイザー
2012『劇場版 SPEC~天~』 VFXスーパーバイザー
2012『エイトレンジャー』 VFXスーパーバイザー
2013『くちづけ』 CGIディレクター
2013『劇場版 SPEC~結~ 漸ノ篇/爻ノ篇』 VFXスーパーバイザー
2014『エイトレンジャー2』 VFXスーパーバイザー
2014『物置のピアノ』 VFXプロデューサー
2015『天空の蜂』 VFXスーパーバイザー
2016『真田十勇士』 VFX監修
2018『人魚の眠る家』 VFXプロデューサー
2019『Diner ダイナー』 VFXスーパーバイザー
2020『望み』 VFX監修
2021『ファーストラヴ』 VFXプロデューサー
2021『胸が鳴るのは君のせい』 VFXスーパーバイザー
2023『ゲネプロ★7』 VFXプロデューサー
2023『映画『ミステリと言う勿れ』 VFXスーパーバイザー
Supported by Enhanced Endorphin
INTERVIEWER : 野口光一(東映アニメーション)
EDIT : 日詰明嘉
PHOTO : 弘田充
LOCATION :N-DESIGN







