トレンド&テクノロジー / デジタルコンテンツの未来〜温故知新〜
第11回:田中 誠一(CGディレクター/アニメーター)
- VR
- アニメ
- コラム
- 映画・TV

CGと縁の深い方々にお話をうかがい、デジタルコンテンツの未来を見通していく記事をお届けする本連載。今回はJCGLやオムニバス・ジャパンで長年勤務し、CGの歴史上重要な『子鹿物語』や『レンズマン』、そして『攻殻機動隊』、『劇場版エヴァンゲリオン』など錚々たる作品に携わった田中誠一氏に登場していただいた。制作当時のエピソードはもちろん、現在もなおVR(XR)コンテンツで精力的に創作活動を続ける氏のクリエイティビティの足跡を聞いた。
【聞き手:野口光一(東映アニメーション)】
Supported by EnhancedEndorphin
「記憶」をテーマにVRワールドの構築を
東映アニメーション/野口光一(以下、野口):今回、田中さんにお話を伺おうと思ったきっかけは、VRのSNS「cluster」で、「水着で来れるビーチ、キャンプ場付き。但し秘密基地あり。」というワールドを見かけたことでした。まず、田中さんがこれらVRに関わるようになったきっかけからお話いただけますか?
cluster : Beach and camp_sites, but with secret bases Ver 1.0
https://cluster.mu/w/7bfd8365-8852-4c39-9efd-bf5ec0b623cb
田中誠一(以下、田中):知り合いのプログラマーとUnityを触って遊んでいるうちに、「人の心を動かし、面白いと感じさせるものは何なんだろうか?」ということへの興味が湧いてきて、検証したくなったことがきっかけです。VRでそれを模索するなか、「記憶」というテーマに関心が向きました。以前、押井守監督の作品に携わったときに「人は映像を記憶で見ている」という命題をいただき、それに準じた印象映像を作ろうとした経験があるのですが、そのテーマをずっと引きずっていて。普通のVRにはあまり存在しないワールド、例えば「居酒屋のワールドで落ち着くのはなぜだろう?」といった感覚の根源を探りたくて、自分自身でもワールド制作を始めました。最初は『科学忍者隊ガッチャマン』の三日月サンゴ礁のようなものを作ろうとしていたのですが、ビーチの中の秘密基地を作っているうちにデータが大きくなりすぎて、弾かれてしまったので、秘密基地は外側だけ残して中身は空っぽにし、ビーチの方をメインに作っていったかたちです。
野口:もともと「記憶と映像」をエンターテイメントの形にしたいという思いが強かった?
田中:僕がVRでワールドを作りたいと思ったときに、ちょうど「cluster」がそれを実現できるプラットフォームとして登場して上手くタイミングが合ったんです。ツールはUnityかUnreal Engineか迷いましたが、まずはUnityから始めました。ちょうど3年目を迎え、clusterで使えるギミックも増えたので、容量の許す限り新しい仕掛けを盛り込んでみようかなと思っています。

野口:VRの現状についてはどうお考えですか?
田中:VRをやる人はずっと続けていますし、インスタンスの数の問題はありますが、小ぢんまりとしたサークルが集まる場としては定着していると思います。ヘッドマウントディスプレイも進化して性能が上がっていますし、遊び場としてちゃんと続いているし、なくなることはないと思います。
野口:VRの先にあるARについてはどうでしょう?
田中:ARがもっと手軽になれば面白いですよね。今のヘッドマウントではなく、街中でかけられるようなメガネ一つでARが実現できれば。Metaもグラス型デバイスを作っていますし、まだ少し見づらさはありますが、改良されればすぐにでも実用化されそうです。グラス型デバイスで、本当に空間に情報が浮かび上がるホログラムのような体験ができれば素晴らしいですね。以前、そういうスタートアップもありました。そういう時代が来ると期待しています、アニメの『電脳コイル』のようになればいいと思いました。あと、一方でUEも気になっています。『フォートナイト』のUEFN(Unreal Editor for Fortnite)で簡単に島を作れるツールがあって、それでリゾート島のようなものを作ってみたんですが、公開までには少し時間がかかるようです。その前に、Pythonを勉強しようかと。AIにPythonのコードを生成させて、それが本当に使えるのか検証してみたいと考えています。Chat GPTのようなAIに「こういうものを作って」と指示すればコードは出てきます。ただ、それが正しいとは限らないとプログラマーの知人も言っていました。AIが勝手に最適化して、関数の効率を優先するあまり、細かい部分で非効率な処理をすることもあるようです。それでも、コードを素早く生成してくれるのは魅力ですね。
野口:現在、PythonやAIはどのような分野で試されているのですか?
田中:UEやBlenderのノードベースのプログラミングで使えないかと考えています。まだ他人が作ったものを書き換える程度で、僕が一から作るわけではありませんが、きちんと構造を理解するために学び直したいと思っています。

手描きアニメーターから黎明期のCG業界へ転身
野口:田中さんは元々理系のご出身ですか?
田中:いえ、東京デザイナー学院の映像アニメーション科です。アニメーションの撮影希望で技術系のことをやりたかったのですが、最初はアニメーターとして就職し、動画を1年ほど担当しました。ただ、原画に進む前に体調を崩して辞め、旭プロダクションという撮影の会社に入りました。
野口:そこからJCGLに移られた経緯を教えていただけますか?
田中:JCGLと同じくエムケイのグループであるビジュアル80という会社が『子鹿物語』(1983〜85年)を制作するにあたり、レイアウトや背景のスキャンニングができる人間を探していて、カメラを使えるということで、私に声がかかったんです。当時、撮影会社の同僚と、TVでロバート・エイブルの『シカゴ』を観て、ワイヤーフレームの世界をアニメに導入できないかと話したり、「これをアニメ制作に導入して、『サイボーグ009』の加速装置を表現できないか?」と話したりしていたので、CGに興味はあったので、一も二もなく向かいました。
ロバート・エイブルの『シカゴ』……1937年クリーブランド生まれ。ジョンホイットニーの弟子として、1950年代にコンピューターグラフィックスの仕事を始め、『2001年宇宙の旅』の視覚効果を手がけた一人であるコン・ペダーソンと1971年にRobert Abel and Associates(RA&A)を設立。『シカゴ』はEvans&Sutherlandを使って制作されたワイヤーフレームによる建築ビジュアライゼーションの先駆けとされる重要な作品。

野口:JCGLでは、どのような業務を?
田中:最初はレイアウトや背景のスキャンを担当していました。当時は白黒の撮像管カメラだったんです。それでフィルターをRGBに交換しながら3回撮影してカラー画像を得るというアナログな手法で、それをディアンザ社製のフレームバッファに取り込み、データをフロッピーディスクの親分のようなものにコピーし、VAX-11本体に持っていく。そんなふうに、今で言うところのコンポジットのような仕事もしていました。当時のJCGL業務は2D主体だったので3Dはほぼ手つかずだったのですが、その後、ニューヨーク工科大学(NYIT)からインストラクターが来て、3Dのデモンストレーションを見せてくれたんです。VAX-11の中にPOLYGONとPRIMITIVEで画像を生成できるソフトも含まれていると聞き、真夜中に大口(孝之)さんと、こそこそと英語のマニュアルと格闘しながら触っていました。大口さんはポリゴンでモデリングできるソフト(POLY)を、私はPRIMITIVE(球、円柱、円錐)でモデリングをして遊んでいました。まだ専用のモデリングツールというものが存在しない時代で、コマンドラインでモデリングしていました。
撮像管…光信号を電気信号に変える特殊な真空管。テレビカメラなどに利用されていた。現在は暗視カメラなどに使われている。

野口:最初の本格的な3DCGの仕事は何でしたか?
田中:最初に作ったのは宇宙船だった気がします。『SF-DEMO』(仮称)という作品用に宇宙船を作ってみて、ぐるぐる回したり、そのあたりから、架定舞台(ヴァーチャルステージ)を設定して逆算すれば、PANするようなカメラワークができることに気が付いて、FOLLOWーPANをするものを作ったところ、金子(満)社長が見てくれて、『SF新世紀レンズマン』(1984年)のチームに入れてくれました。当時はUIがキャラクターディスプレイだけしかなく、たとえば『レンズマン』の主人公を追尾するカメラワークを作るにしても、とても手間のかかる方法でした。ダミーの3D人形を走らせてフィルムレコーディングし、それを1フレーム毎に紙焼きしてもらい、手描きのアニメーターにキャラを乗せてもらって、オプチカル合成するというプロセスが必要でした。
野口:この時期、どのようなことをCGに期待されていましたか?
田中:エフェクトに興味がありました。モーションブラーもどきの効果を出したり、心象のエフェクトができないかいろいろ実験をしていました。レンダラーはいじれないので手持ちのものです。3DCGを生で使うのではなく、どうしたらアニメの力となれるのかは、このころからよく考えるようにはなりました。

『パトレイバー』、『攻殻』、『エヴァ』……オムニバス・ジャパンで携わった数々の'90年代の名作アニメ映画
野口:JCGLにはいつまでいらっしゃったんですか?
田中:解散までいました。機材がどんどん売られていくのを寂しく見ていた記憶があります。その後、オムニバス・ジャパンに誘われました。当時はPRISMSやAlias社のPower Animator(IRIS3130)のシステムがあり、両方のチームが存在していました。またスタッフとして、カナダのOmnibusに在籍されていたGORDONさんや、その後フランスのExMachinaから何人か来られ、国際色豊かな環境でした。当時オムニバスでもTDI Exploreという3Dソフトも一時期使っていました。
野口:オムニバス・ジャパンでは、どのようなお仕事を?
田中:CMとかCIが多かったですね。最初はAliasで研修を受け、使えるようになった頃には、師事していた小高(忠男)さんがバンプレストに移籍してしまい、Aliasチームの戦力が手薄になっていました。そこでPRISMS班に移ることになりました。
野口:オムニバスといえばPRISMSという印象があるのですが、そういう事情だったんですね。
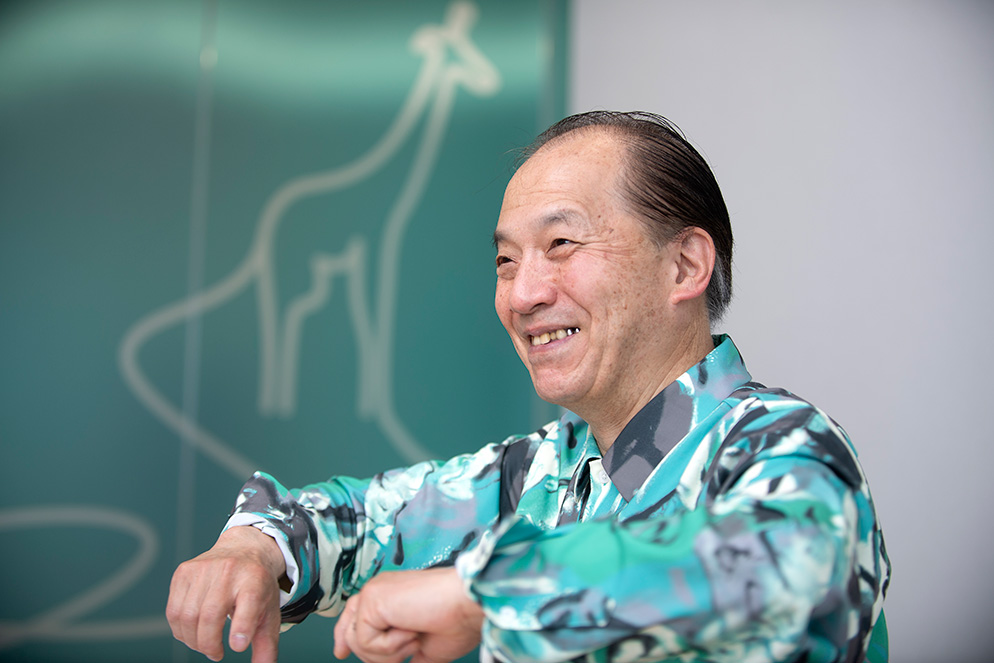
田中:あとはNHKの『人体』(1989年)の一部や、世界デザイン博(1989年)のトヨタ館でライド映像を作ったり、『機動警察パトレイバー 2 the Movie』(1993年)、『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』(1995年)、『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に』(1997年)の、アニメのCGディレクター仕事が続いていきました。『G.R.M.』パイロット版『アヴァロン』(2002年)ではオムニバスパートのCGディレクターを担当しました。
野口:『攻殻機動隊』の時はフィルムレコーディングですよね?
野口:そうですね。高解像度のフィルムパートと、D1-VTRのビデオテープに落としてそれをビデオ編集所で加工してから最終的にフィルムレコーディングするビデオパートに分かれていました。高解像度よりも滲みや歪みが求められました。その頃のCRTで映像を観ている時の心象に結びつけたかったと思います。それが先程の「記憶で見ている」に繋がる部分だと思います。
野口:『エヴァ』のスタッフロールは当初からああいった演出の予定だったんですか?
田中:そうですね。庵野(秀明)総監督の絵コンテの段階から普通ではない見せ方を意図されていたように感じました。当初は白黒の文字がただ回転するだけというシンプルなものだったんですが、担当がわざと間違えて、世界観に合うようなオレンジ色のフィルターをかけてみたところ、庵野さんも似た方策を考えていたようでそれが採用されたんです。文字に関しては先方からPDFでスタッフリストをもらって、softimageの機能で3Dに起こして回転させ、レンダリングした素材にフィルター処理を施し、さらにハイライト部分を別素材で作って重ねるなど、工夫を凝らしました。フィルムレコーダーを巻き戻ししながら3回撮影するという手法なのですがスタッフはなしとげてくれました。もし修正箇所が出たら、その部分の前後のかなりの尺を撮りなおし、差し替えるという作業が必要になりました。
野口:オムニバス・ジャパンは編集スタジオを持ちつつCG制作もあるプロダクションというのが強みだったと思うのですが、あれは当初から意図されたものだったのでしょうか?
田中:そうですね。東北新社の社長だった植村伴次郎さんの構想だったと思います。初期のころ英国クオンテル社のハリーを導入し、それを若き頃の中島信也さんが面白がって使い倒してくれたことも大きいと思います。同時に業界的にFtoTが流行りだして化粧品会社などが注目してくれたことも大きいかもしれません。その後アニメ的には押井さんがDOMINOを何回か使ってくれました。ABロール編集が主流だった時代に、劣化しないデジタル編集は画期的で、特に化粧品などのCMクライアントに喜ばれたようです。
中島信也……CMディレクター。代表作に日清食品 カップヌードル 「hungry シリーズ」など。
野口:2000年以降はどのような活動をされていたのですか?
田中:CGの現場に本格的に参加した最後の作品は『PARTY7』(2000年)でした。その後も『WXIII 機動警察パトレイバー』(2002年)や『宇宙戦艦ヤマト 復活篇』(2009年)などで少し手伝いをし、その後はDVDやBlu-rayのオーサリング、その後はデジタルサイネージのデータ変換などの仕事をしていました。そして60歳を迎えました。

AIと相性が良いパーソナルな表現とXR技術を応用した着せ替え世界
野口:最後に、田中さんの興味の対象についてお聞かせください。やはりAIでしょうか?
田中:やはり今後AIどう活用していくかが重要だと思います。AIで直接絵を生成するというわけではなく、例えば知り合いのSV方は背景の物量的に必要なものを生成させて3Dモデル化するなど、空間制作の補助としても様々な使い方をしているそうです。またAIはよりパーソナルな表現に寄り添えるものを可能にする表現だと思います。究極的には本当に個人向け、唯一あなただけのカスタマイズも可能かもしれません。
一方で、アニメーションのようにさまざまな人が連携して面白いものを作り上げるというメディアはなくならないと思います。やはり『葬送のフリーレン』や『鬼滅の刃』のような大ヒットアニメ作品は、多くの才能が集結して生まれるものですから。AIは過去のデータから学習しますが、人間のように多様な人生経験から生まれる独創的な組み合わせや、全く新しい表現を生み出すのはまだ難しいかもしれません。ただ、AIが人格を持ち、自ら創造を始めるようになれば、人間とAIがスタッフとして協業する未来も来るかもしれませんね(笑)。
野口:ツールという意味で、AIと付き合うことは今後も不可欠になりそうですね。
田中:AIは「変なモノ」を生成できないでしょうね。「モノ」というの観測者がいて初めて価値を持つように、「変なモノ」が生成されたときに、「これは面白い」と判断して発表する人がいることで評価を獲得することになります。昔は誰が見ても「スゴい」と思える斬新な映像がありましたが、今は情報も技術もあふれています。その中で何が本当に新しいのかを判断する目も必要になってくるでしょう。
野口:今後目指していることは?
田中:現実とシームレスなVRやAR、XRですね。これは今までやってきた、アニメ、CG、SFX、VFX、オーサリング、サイネージ、およびデザイン等の技術を集大成にできるものです。例えば、現実世界の風景や通行人や車などを、自分の好きな世界観に描き換え、現実をSF世界のように表現するという試みです。そのためにはXR技術がスマホ並みに普及している前提であったり、AIを使った描き換えに膨大な計算処理が必要だったりと、まだまだ未来の話ですが、すでにいろいろなところで足並みがそろい始めている気がします。先程も申しましたように、AIはパーソナルにカスタマイズされたコンテンツの制作と相性が良さそうな気がします。そこまで行かなくとも自宅の部屋ぐらいの規模であれば、好きな作品と同じ部屋をcluster内で再現してVRヘッドマウントディスプレイを付けたまま、寝転んだりくつろげるワールドを構築することはできそうなので、徐々に試しつつ反応を見てみようかと思います。その制作過程でAIとの相談事はかなりの刺激になりそうです。冒険はやめない限り続けられるのですね。

田中 誠一 氏
CGディレクター、アニメーター、デザイナー、プログラマー
1982年より株式会社コンピュータ・グラフィック・ラボ(JCGL)にてアニメーター、支援プログラマー、デザイナーとして活動を開始。1988年からはオムニバス・ジャパンに所属し、CG/VFX/アニメーター、デザイナー、ディレクターなど多岐にわたる役割を担当。代表作品として 『機動警察パトレイバー2 the Movie』(1992年 CGディレクター )、『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』(1995年 CGディレクター、アニメーター、オープニングデザイン)、 『新世紀エヴァンゲリオン THE END OF EVANGELION』(1997年 -CGディレクター)、 『AVALON』(1999年 CGディレクター、アニメーター、オープニングデザイン)などがある。近年では、VR/ARストーリー表現の実現を目指すグループ「VC_LAB」を主催し、2025年6月にはVRプラットフォーム「Cluster」にて構築したワールドに29,000人以上が来訪している。
フィルモグラフィー
1984年 劇場用アニメ映画 「SF新世紀レンズマン」
1985年 つくば科学万博「バイオ星への旅」
1989年 NHK 驚異の小宇宙 人体 デザイナー/アニメーター
1992年 劇場用アニメ『機動警察パトレイバー2 the move』CGディレクター
1995年 劇場用アニメ『GHOT IN THE SHELL 攻殻機動隊』 CG(DGA)ディレクター/アニメーター/OPデザイン
1996年 劇場映画 「あぶない刑事・リターンズ」CG/VFX オムニバスパート/ディレクター
1997年 劇場用アニメ『新世紀エヴァンゲリオンTHE END OF EVANGELIONAir/まごころを、君に』オムニバス・パートCGディレクター
1997年 劇場用アニメ『機関車先生』 CGパート/CGディレクター
1997年 劇場版アニメ『フランダースの犬』 CGパート/CGディレクター
1998年 パイロット版『G.R.M.』オムニバス・パートCGディレクター/アニメーター
1998年 劇場用アニメ『WXIII PATLABOR THE MOVIE』 CGスーパーバイザー
1999年 劇場用映画 『AVALON』オムニバス・パートCGディレクター/アニメーター/OPデザイン(協力 松本薫)
2000年 劇場用映画 『劇場用映画 『PARTY7』 CGディレクター
Supported by Enhanced Endorphin
INTERVIEWER:野口光一(東映アニメーション)
EDIT:日詰明嘉
PHOTO:弘田充
LOCATION:東映アニメーション







